【値上げ2025】に慣れたふりしてるけど、やっぱキツい
この記事を読むと何が変わる?
- 「なんとなくキツい…」と感じている理由が言語化できる
- 値上げラッシュの中でも、心を削られにくくなる考え方がわかる
- 節約だけに頼らない、「設計」で乗り切る視点が手に入る
パン、コーヒー、ガソリン、外食、日用品。
気づけば、ほぼ全部が2025年も静かに値上がりしています。
ニュースでは「値上げ」「物価上昇」という言葉を聞きすぎて、
正直、少し麻痺してきている人も多いはずです。
でも、レジで支払う金額を見た瞬間、心のどこかでこう思いませんか。
「やっぱり、キツいよな…」
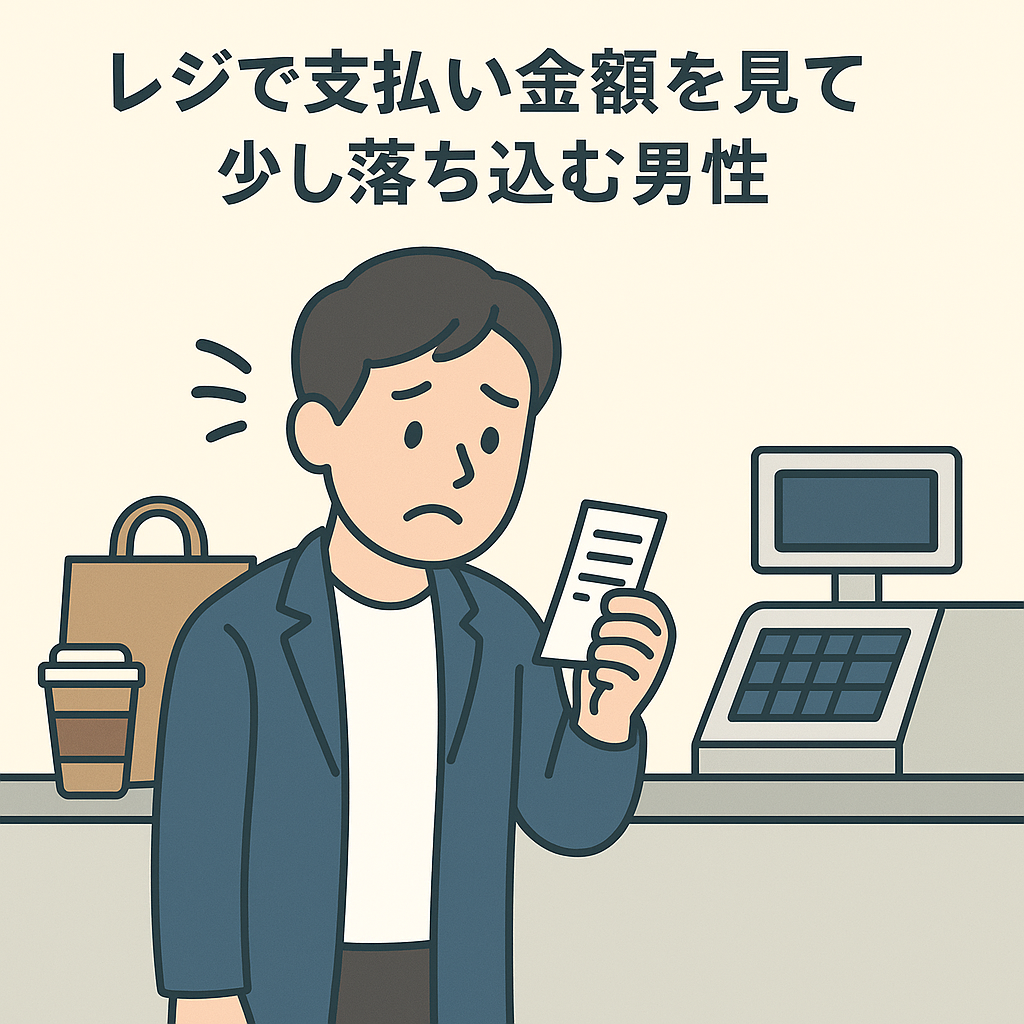
シンプルヒーローズについて
私は本業で建設系の仕事をしながら、
副業でブログ運営やお金の使い方・時間の使い方について発信しています。
現場の仲間たちから「最近ほんとに生活がキツい」という声を、
毎日のように聞いてきました。

この記事はこんなあなたのためのものです
- 「値上げ慣れ」してきたけれど、内心は焦っている
- 給料はほとんど変わらないのに、支出だけ増えている
- 節約はしているつもりなのに、手元に残らない感覚がある
- 将来のお金の不安が、じわじわ心を重くしている

「慣れたふり」をしているけど、本音はしんどい
私自身、コンビニで昼ごはんを買ったときに、
「え、これで1,000円超えるの?」と何度も驚きました。
コーヒーを購入しても、スーパーで少し買い足しても、
支払いの合計金額だけが、静かに右肩上がり。
友人や同僚と話すときは、
「まあ、どこも値上げしてるしね〜」と笑ってごまかす。
でも、心の底では「このままで大丈夫か?」という不安が消えませんでした。
1. 「少しずつの値上げ2025」が生活をむしばんでいく
■ 小さな値上げほど危ない
一回ごとの小さな値上げは、「大したことない」と思えてしまうからこそ危険です。
■ 人は損失の変化に鈍感になる
行動経済学では、人は「少しずつの損失」に鈍感になると言われます。
カエルをぬるま湯から徐々に温度を上げて茹でてしまうたとえ話に近く、
気づいたときには取り返しのつかない負担になっている、という現象です。
■ 少額でも積み重ねは大きい
正直、私も最初はこう思っていました。
「パンが10円上がっても、まあいいか」「コーヒーも毎回数百円の違いだし…」と。
ところが、あるとき1か月分のレシートを集計してみたら、
前年同月よりも1万〜1万5千円ほど支出が増えていたんです。
「たかが10円」「たかが数十円」が、積もり積もってこの金額。
そこで初めて、
「あ、慣れたふりしてる間に、ちゃんと生活が削られてるな」と実感しました。
「いや、そんなに変わってないよ」と思う気持ちもよくわかります。
ですが、一度数字で見てしまうと、
「何となく大丈夫」という感覚が、かなり危ういものだと気づきます。
■ 数字で確認するのが最初の一歩
だからこそ、「少しずつだから大丈夫」と流すのではなく、
数字で一度確認してみることが、第一歩になります。
2. 「仕方ない値上げ2025」が口ぐせになると、思考が止まる
■ 「仕方ない」で思考停止が始まる
「仕方ないよね」と自分に言い聞かせ続けると、対策を考える力そのものが弱まります。
■ 無力感が判断力を奪う
心理学では、何度もコントロール不能な状況を経験すると、
「どうせ何をやっても変わらない」という気持ちになり、
行動する意欲が低下することを「学習性無力感」と呼びます。
値上げニュースを見続け、
自分の給料は変わらないまま…という状況が続くと、
「文句を言ってもしょうがない」「我慢するしかない」と、
心があきらめモードになってしまうのです。
■ 外を責めても現実は変わらない
私も一時期、「国の政策が悪い」「会社の給料が上がらない」と、
外側の問題ばかり責めていました。
正直、その気持ちは今でもゼロではありません。
でも、そこで思考が止まっていた時期は、
家計簿をつけても現実が変わらないし、
副業について調べても行動に移せない。
「どうせやっても無駄」という前提で動いていたからです。
「いや、こっちが頑張っても、どうにもならないでしょ」という声も理解できます。
ただ、少なくとも
・固定費を1〜2個減らす
・収入の柱を一本だけ増やす準備をする
といった行動は、
「完全に無力」ではない証拠にもなります。
■ 小さな行動で無力感から抜けられる
「仕方ない」を口ぐせにするのではなく、
“自分にできる範囲”だけでも動いてみる。 その小さな一歩が、無力感から抜けるきっかけになります。
3. 「設計」を変えれば、値上げ2025のストレスは確実に減る
■ お金の設計で不安は減らせる
値上げそのものは止められなくても、 お金の流れの“設計”を変えれば、感じるストレスは確実に減らせます。
■ コントロール感が安心を生む
人は「コントロール感」があるだけで、ストレスの感じ方が大きく変わるとされています。
同じ支出でも、「なんとなく減っていく」より、
「自分で決めたところにお金を流している」と感じられれば、
不安はぐっと小さくなります。
■ 生活の流れを書き出すと変化が起きる
私も以前は、給料が入ったら「なんとなく使って、なんとなく減っていく」感覚でした。
しかし、
- 固定費(家賃・通信・保険)をまず整理する
- 毎月“自分のため”に使う金額を先に決めておく
- 残りを生活費と貯金に振り分ける
というシンプルなルールを作っただけで、
同じ給料でも「足りない不安」がかなり減りました。
「そんなの当たり前じゃない?」という声もあると思います。
でも、頭ではわかっていても、
実際に“設計図レベル”でお金の流れを書き出している人は、意外と少ないです。
■ 流されず、流れを決める
値上げの波にただ耐えるのではなく、 自分なりのお金の流れを設計しておく。
それだけで、同じ物価でも感じるしんどさは確実に変わります。
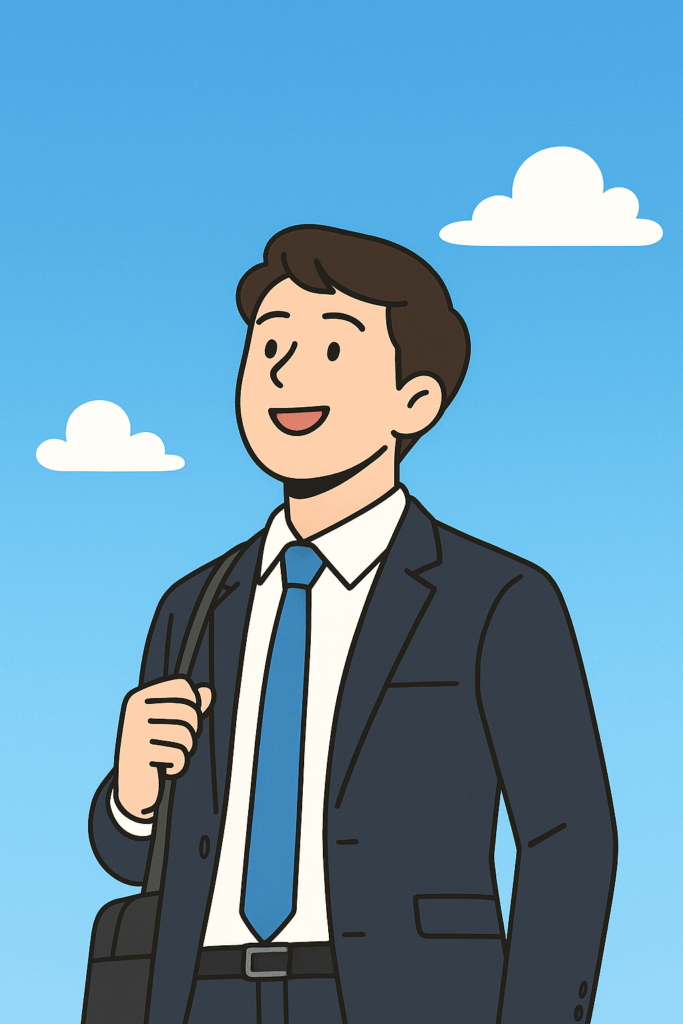
まとめ:慣れたふりをやめた瞬間から、人生の主導権が戻ってくる
- 少しずつの値上げは、「大したことない」と思えてしまうからこそ危険
- 「仕方ない」が口ぐせになると、学習性無力感で思考が止まる
- 値上げは止められないが、“設計”を変えることでストレスは減らせる
【値上げ2025】の現実は、たしかに厳しいです。
それでも、「慣れたふり」をやめて、 数字を見て、少しだけ設計を変えてみる。
その小さな一歩が、 数年後の「やっておいてよかった」という未来につながると、 私は本気で思っています。
では、また🤙



コメント